『ウォール・オブ・サウンド』 希望と絶望が同居したようなフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」にまつわる誤解 [世界のロック記憶遺産100]
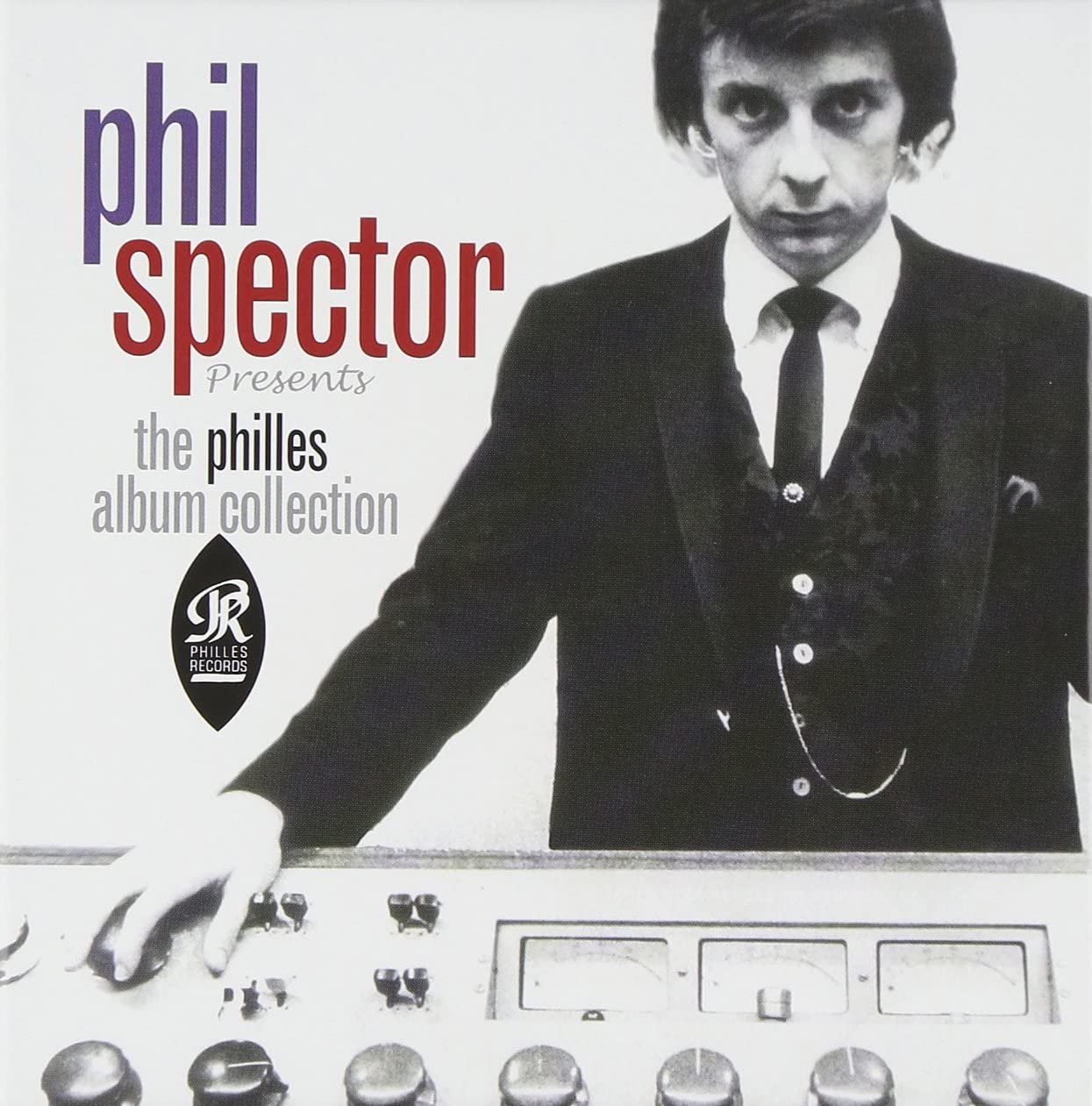
フィル・スペクターが亡くなった。ウォール・オブ・サウンドという後のシューゲイザーの音を表したかのような名前、テクノ時代にウォール・オブ・サウンドというレーベルが生まれたように、どれだけイギリス人がフィル・スペクターを気にしていたのかよく分かります。こんなこと思ってるの僕だけかもしれませんが。
もちろん日本では大瀧詠一、山下達郎がいます。
でもこのウォール・オブ・サウンドってすごい誤解があるような気がするのです。ウォール・オブ・サウンドという名前から音の壁を作ってみたいな印象があるかもしれないですが、が音の壁を作ろうとしていたかどうなのか、それは謎です。
ベーシストを二人使ったりして音圧を稼ごうとしていたのかもしれませんが、僕は彼のサウンドがなぜウォール・オブ・サウンドって言われていたかというと、彼のレコーディング方法がびっくりするくらいパーティション(防音の壁)で囲われていたからなのではないかと思うのです。
よく映画なんかで観る一人一人がアメリカのオフィスのような壁で隔てられた場所で録音しているの様子を観て、スタジオ・ミュージシャンが“ウォール・オブ・サウンド”って揶揄したことから、彼の特殊な音はウォール・オブ・サウンドって呼ばれようになったような気がしてならないのです。
それを誤解してシューゲイザーなどは音の壁を作るようになったのです。
その一番の始まりはラモーンズですけどね。
ラモーンズがなぜそんなことをしたか、それは彼らはアメリカの50年代や60年代のポップスが好きだったけど、でもその音はどこか甘ったるい音の洪水のように感じていたからではないでしょうか?“こんなかっこいヴォーカル、ギター、ベース、ドラム入っているのに、なんでこんな甘っちょろいストリングス入ってんねん、ちゃうねん、俺らが欲しいのはベートベンのようなハードなクラシック・サウンドやねん、その感じをギターでグワーンとやったらカッコいいいちゃうの、めっちゃ受けるで”とやったのがラモーンズだったんじゃないのか僕は妄想するのです。
全然売れなかったですけどね。
多分フィル・スペクターがやっていたこともこれなんだと思うのです。“フランク・シナトラや軍隊に行ってからのエルヴィス・プレスリーの音は生っちょろいねん、もっとドラムは大きく、ファンキーにそういう音楽をやりたいねん”とやっていたのがフィル・スペクターなんじゃないかと思うのです。
もちろんフィル・スペクターの音楽の中には甘いのもあります。元々ザ・テディベアーズというグループ名の人ですからね。彼はまず売れるためには甘っちょろいこともしないといけないだろと理解していたんだろうと思います。
ザ・テディベアーズが売れて、自分のレコード会社を作り初のティーンエイジ・ミリオネア(ティーンエイジより歳をとってたと思いますが)になった彼が本当に自分の望む音を作ったその音楽の代表がロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」でした。
そして甘っちょろいのとハードなものが見事に組み合わさった傑作がライチャス・ブラザーズの「ふられた気持」です。『ツィン・ピークス』のようなダークで甘い世界感、これは今のアメリカのポップスが今もずっとやっていることです。これがアメリカで売れる秘訣なんだと思います。今のアメリカのベスト10の音楽なんてみんなこれですよ。ヒップホップなんでビートはハードですが、音と歌詞の世界はダークでクリーピー、今の日本のポップスも一緒ですけどね。
聴いてると世界が終わるんじゃないかと思えるようなサウンドです。希望と絶望が同居したようなサウンド、それはロックンロールやブルースとは違ったようなサウンドです。ロックンロールとかブルースの白人的解釈だったような気がします。
だからイギリスや日本では永遠に愛されているんでしょうね。
フィル・スペクターはこういう音楽を目指していたわけです。永遠の14歳のサウンド、キラキラしてるけど、どこかドロドロしてる、いつまでも答えがないようなサウンド。
彼はその音楽を作るために、普通のプロデューサーより多めにエコー・チェンバーをかけるようにしていたのです。

(残り 1517文字/全文: 3277文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。
タグマ!アカウントでログイン
tags: Phil Spector












外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ