赤線の女たちを恐ろしい闇路へけおとしたのは誰か-廃娼運動は人権運動ではなかった [ビバノン循環湯 7] (松沢呉一) -5,793文字-
「娼婦の無許可撮影をするゲス写真家は今に始まったことではない」でとりあげた『危険な毒花』『月蝕』の2冊の本に対して、「肖像権なんてものが確立していなかったのだからしょうがない」という弁護は成立しないことを「カフェー女給と娼妓の写真に見るモラル・・・」 で確認しました。昭和20年代にはすでに勝手に写真を撮って勝手に公開してはいけないという感覚が広く浸透していて、裁判上もその方向で動き出していました。
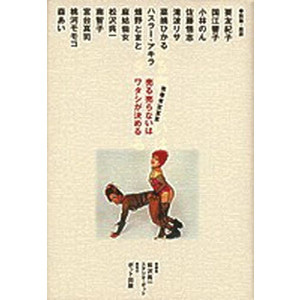 では、なぜ写真家たちは法もモラルも無視して、赤線の女たちにああもゲスなことができたのでありましょうか。
では、なぜ写真家たちは法もモラルも無視して、赤線の女たちにああもゲスなことができたのでありましょうか。
その時代の赤線がどういう状況にあったのかを知っておく必要がありそうです。改めて書こうと思ったのですが、過去にさんざん書いてきてますので、そのことがわかるものを出しておきます。
ここで私は赤線の女たちの立場から見ているわけですが、その女たちの生活を踏みにじった者たちがいます。売春防止法(1956)を制定した政治家たちであり、婦人運動家であり、宗教活動家です。ここに具体的に名前が出てきているのは、神近市子や伊藤秀吉です。昭和20年代前半までは赤線の女たちに世論は同情的でしたが、この頃には世論もまた売防法を容認。
 写真家たちはそちらの立場にいたのだと思います。売防法同様、売春をする女たちの人権や生活など踏みにじってもいいのだという立場です。
写真家たちはそちらの立場にいたのだと思います。売防法同様、売春をする女たちの人権や生活など踏みにじってもいいのだという立場です。
売防法は働く女たちの人権のために制定されたと誤解している人たちがよくいますが、まったく違います。赤線の従業員組合は顔を晒して街頭に出て訴え、政治家への陳情もして売防法に反対をしたのですが、受け入れられませんでした。
ここに再録をしたのは彼女たちの闘い方は正しかったのかどうかを論じた一文です。十年以上前にネットに出したものだったと思います。
 前提になる廃娼運動、売防法、赤線組合、神近市子といったワードを理解していないと意味がわかりにくいかと思いますが、それぞれ細かく論じた文章は他にあるため、すでにそういうものを読んでいる人を対象に書いています。そういった文章もまた機会があれば再録しますけど、今日のところはわかる人だけ読んでいただければ。あるいは明日更新分を読んでから、こちらを読んだ方がわかりやすいかもしれない。
前提になる廃娼運動、売防法、赤線組合、神近市子といったワードを理解していないと意味がわかりにくいかと思いますが、それぞれ細かく論じた文章は他にあるため、すでにそういうものを読んでいる人を対象に書いています。そういった文章もまた機会があれば再録しますけど、今日のところはわかる人だけ読んでいただければ。あるいは明日更新分を読んでから、こちらを読んだ方がわかりやすいかもしれない。
なお、私が編集した『売る売らないはワタシが決める―売春肯定宣言 』にも新吉原女子保健組合のことに少し触れています。また、『ワタシが決めた 』は新吉原女子保健組合による文集『明るい谷間』に触発されたものです。右の書影は復刻版。オリジナルもうちのどっかにあるのですが、すぐには出てこないので、これで勘弁してください。
「婦人新風」も復刻が出ていますが、解説がひどい。よりによって組合の意思を踏みにじった勢力に解説さすなよ。
赤線従業婦組合の必死の訴え
![]() 赤線従業婦組合を代表する存在であった新吉原女子保健組合の機関紙『婦人新風』創刊号掲載の「発刊に際して」にこんな言葉がある(組合長・大湖礼子によるもの)。
赤線従業婦組合を代表する存在であった新吉原女子保健組合の機関紙『婦人新風』創刊号掲載の「発刊に際して」にこんな言葉がある(組合長・大湖礼子によるもの)。
もはやこの街は、私達にとって堕落の街ではなく第二の人生への更生の修練場であり、組合はここに働く人々の心のより所として、強い背骨をうちたてようとしております。
この更生という言葉を、売防法に反対する過程で彼女らは繰り返し強調していく。
私たちの味方であるべき婦人議員は、私たちの救済、更生施設どころか、私たちの比較的安定の場所である赤線地区の業者と共に、私たちを暗い恐ろしい闇路へけおとす為に売春の禁止法案を提供しようとしております。(1956年・昭和31年1月12日に浅草公会堂で開かれた「東京都女子従業員組合連合会」の結成式における挨拶より)
私達は、政治の貧困による被害者であり、一日も早く政治の貧困よりの解放を念願しているのであります、更生への悲願は夢の間にも忘れ得ない私達の胸にやきついている事実であります。従って、私達は、更生保護の途が開かれ、私達に大いなる希望と光明を与えられ、以って不安の念を一層されんことを強く熱望するのであります。(1956年・昭和31年2月17日に東京女子従業員組合連合会が国会に提出した陳情書より)
自ら更生という言葉を使うことに対して、詩人で小説家の関根弘は『小説吉原志』(1971年・講談社)でこう書いている。
なぜ転業といわないで、更生といったのだろう。売春は、職業ではなく、もともと<非行>とかんがえているからではないか。非行という観念をおいて更生をかんがえたとき、彼女たちはほんとうの意味での更生の道をみうしなったのではあるまいか。そうならば、どうすればよかったか。
ここにある「ほんとうの意味での更生」という言葉がよく理解できないのだが、このように、赤線組合はより明確に自分らの存在を正面から肯定すべきだったとの意見を言う人もいる。私も以前はそう考えていた。
たしかに、自ら売春を必要悪とし、被害者としての救済を求めることは、それ自体を取り出せば、決して賢明ではなかった。いつかなくなればいいものでしかないのなら、すぐになくせばいい、しかし、現に働いている人がいるのだから、「更生」させよう。こういう流れで、売防法はいくらかの修正を加えつつ成立を迎え、現実には「更生」する間もなく娼婦たちは「暗い恐ろしい闇路」へけおとされたのだ。
しかし、どうすればよかったかについて、今の時代に振り返って的確な代案を提示することは難しい。当時も同様だったろう。
もし彼女らが働く権利を前面に押し出していたのであれば、いよいよ強いバッシングを受けただろうし、そのことをも悪用するくらいに売防法推進派は狡猾であった。世間一般も売防法制定容認に向かいつつある中で、組合は必要悪としての防戦をするしかなく、彼女ら自身の意識としても、必要悪以外に自分らを正当化する発想は出てこなかっただろう。日々の生活に追われつつ、それほどまでに余裕のない中での必死の活動であったのだ。
おかしいのは神近市子の頭である
![]() 彼女らが「更生」「必要悪」という言葉を使ったことを、関根弘が批判的にとらえているのは、それらの言葉に対して売防法を推進する側はウソなのだというキャンペーンを展開したことを背景にしている。
彼女らが「更生」「必要悪」という言葉を使ったことを、関根弘が批判的にとらえているのは、それらの言葉に対して売防法を推進する側はウソなのだというキャンペーンを展開したことを背景にしている。
今更繰り返してもしょうがないが、私達が叫んだ血縁者の実生活の貧困救済と私達自身の更生の叫びが逆用され、殊に神近市子氏の如きは私達の血の出るような真剣の(ママ)叫びに耳を覆い、私達が親子姉妹の貧しい生活の負担や子女の養育に苦しむなどということ、つくられた声であって真実の声ではない。七、八割の女は虚栄心や怠惰から身を落としているものだ(略)ときめつけられてしまった。私達は婦人の味方であるべき婦人代議士連の政治的面子のために明日からの生活を奪われる結果となってしまったのだ。(1956・昭和31年6月20日付「婦人新風」)
組合が、自分たちだって好きでやっているのではない、家族のためにやむなくやっているのだと主張したことに対して、神近市子らはこう反応したのである。
最近、赤線従業婦組合が結ばれ、彼女達から生活権確保の陳情書が殺到しているが、陳情の内容は全て父母が病気だ、夫が病気だ、子供の面倒をみていると同じ訴えばかりである。そこがチョットおかしいとも思える。彼女達の境遇もそれぞれ違っていてこそ意味がある。私は一枚もこれでは信用がおけない。(1956年・昭和31年5月5日付「興信新聞」での談話。1956年・昭和31年5月25日付「婦人新風」からの孫引き)
例外はあったにせよ、赤線の女たちは、さまざまなデータが明らかにしているように、街娼に比べると、ここにあるようなやむなき事情を抱えた率が高い。調べることもせずに法律をゴリ押ししたのがこの神近市子である。「チョットおかしいのは、神近市子、おまえの頭だ」と言わないではいられない。

(残り 2787文字/全文: 6078文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。








外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ