小山いと子が描いた「開かれぬ門」-「吉原炎上」間違い探し 13[ビバノン循環湯 87] (松沢呉一) -3,456文字-
「「悲惨に死ね」と願う浅ましさ-「吉原炎上」間違い探し 12」の続きです。
開かれぬ門はどこに存在するか
![]()
小山いと子著『開かれぬ門』(大日本雄弁会講談社・1958年)という小説がある。著者は1950年に「執行猶予」で直木賞を受賞した小説家。
「開かれぬ門」というタイトルから、どうせ関東大震災の時に、 吉原大門を開かなかったために娼妓が大量に焼け死んだというデマを信じて、売春婦の悲惨物語でも書こうとしたのだろうと思いつつ、資料として購入。
 読んでみたら、180度違う立場から書かれたもので、社会に広くある売春否定の論理が現実にはま ったく通用しないものであることを見事に描いた小説であった。
読んでみたら、180度違う立場から書かれたもので、社会に広くある売春否定の論理が現実にはま ったく通用しないものであることを見事に描いた小説であった。
以下はネタバレになってしまうが、ストーリーを紹介しないとこの小説のどこが優れているのかがわからないだろう。
主人公の不二子は、横浜にある全寮制のお嬢様校の生徒。その美貌から女生徒たちの憧れの的である。 しかし、その身許は謎に包まれていて、長期の休みでも実家に帰らず、軽井沢の別荘に帰る。そこには身の回りの世話をする中年女性がいるだけで、家族はおらず、時折父親が訪ねてくる。親子の接点はそれだけである。
父の桃山権作は吉原で特飲店を営んでいる。そのことを彼女は恥じており、誰にも教えていなかったのだが、父親とは無関係に、軽井沢にもパンパン屋ができる。もとは避暑にくるGIらを対象にしたものだったのだろうが、こういった場所にも売春施設、あるいは売春する個人がいたのは事実。
軽井沢で不二子が恋をした旧華族の青年がパンパンを罵倒するのを聞いて、彼女は思わず反発してしまい、彼にこう言う。
「人夫は腕と肩を使い、大工さんは手を使い、大学の先生は頭を使ってお金をとって ますわ。ほかに売るものもない、学歴もないあわれな女がそうして自分の力で生きて ゆくのを、なぜそう憎まなければならないのでしょう?」
現実を踏まえない論の挫折
![]()
 これを契機に、不二子は父親の権作に仕事を辞めて欲しいと頼み込むが、権作は聞き入れず。不二子は再度交渉するために、生まれて初めて父親が経営する吉原の「茂奈古」を訪ねる。
これを契機に、不二子は父親の権作に仕事を辞めて欲しいと頼み込むが、権作は聞き入れず。不二子は再度交渉するために、生まれて初めて父親が経営する吉原の「茂奈古」を訪ねる。
いざ目にした現実は、自分の頭の中にあったイメージとは違っていた。ここで働く女はぜいたくな暮らしぶりである。 もっとも稼ぐ人は月に四十万円、続いて三十万円前後稼ぐのが二人か三人はいるという。昭和二十年代末のことなので、物価は今の十分の一弱といったところ。
「茂奈古」には大卒や大学中退もいて、不二子がその一人に「ほかの仕事に就きたいと思うでしょう」と聞いたら、こう答える。
「思わない。絶対にそうは考えないわね。これだけの暮らしが出来て、これだけの収入のある女の仕事はどこにもないじゃないの」
自分が思っていた世界、自分が思っていた女たちと違っていたことを知り始める不二子だったが、権作の非道なやり方に腹を立てて、権作に宣戦布告、吉原をなくそうと決意し、店の女たちを廃業させようと画策する。
これ以降、この計画が次々と挫折していく過程を描いていく。女たちをつれていった更正施設は、予算をとるために女たちを利用したものでしかなく、女たちは 監禁状態に置かれ、体裁だけの施設のため、更正させることが容易ではないことを知ることになる。
※どうでもいいけど、吉原大門の近くにある銭湯「堤柳泉」。まだ入ったことはない(その後入った。さっぱりとした清潔感のある銭湯)。
結婚の過酷さ
![]() 稼いでも稼いでも十万円の借金が減らず、「どんなに稼いだって借金は抜けない仕組みになっている」と不平を言うレン子という店の女に、権作は「湯水のように金を使うってお前のことだ。腰巻きからパンツからみんなクリニング屋だ」と叱っている。吉原の女たちは下着までクリーニングに出すという話は、吉原で働いた女の手記にも出てくるエピソードで、事実、そういうのがいたのだろう。
稼いでも稼いでも十万円の借金が減らず、「どんなに稼いだって借金は抜けない仕組みになっている」と不平を言うレン子という店の女に、権作は「湯水のように金を使うってお前のことだ。腰巻きからパンツからみんなクリニング屋だ」と叱っている。吉原の女たちは下着までクリーニングに出すという話は、吉原で働いた女の手記にも出てくるエピソードで、事実、そういうのがいたのだろう。
レン子は月に三十万円を超える稼ぎがあって、それでも十万円の借金が返せない。借金が減らない仕組みがあるのではなく、ただの浪費なのであった。このエピソードに私は深く納得。現在でもそういう風俗嬢が存在している。
「ホストクラブの売掛が膨らんでしまって、仕事を始めました」
「もう返したんでしょ」
「いや、返しても返しても減らないんです」
なんか悪いホストにつかまったのかと思ったら、現在も毎日のようにホストクラブに行っていることが判明。そりゃ、減るわけないだろ。こういうことがよくあるのだ。
このレン子は不二子の勧めで結婚するが、すぐに「茂奈古」に戻って来てしまい、 不二子に恨み言を言う。結婚先の農家ではロクに食事も与えられず、姑にいびられ、 朝の五時から夜の十二時過ぎまでこき使われる。
レン子はかつてはああも非難した権作のことを褒めちぎる。
「あれから見れば天国だわ。私は百ぺんでもいうけれど、不二子ちゃん、あんたここの女を助けるより、農村の嫁さんを助ける方が先決問題よ」
嫁ぎ先では、女は単なる労働力であり、子どもを生む道具でしかなかったのだ。その改善をせずして、売春を否定することの欺瞞を不二子はつきつけられてしまう。

(残り 1478文字/全文: 3628文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





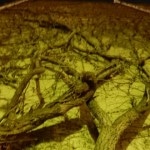


外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ