「にょしょう」から「じょせい」へ—「女子」の用法 5-[ビバノン循環湯 229] (松沢呉一) -2,689文字-
「文学に見る「女」と「女性」—「女子」の用法 4」の続きです。
夏目漱石の作品から
![]() 夏目漱石のいくつかの小説も検索してみましたが、森鴎外と同じく、ほとんど「女性」は使っていません。使っている場合は「にょせう」のルビがあります。「にょしょう」です。
夏目漱石のいくつかの小説も検索してみましたが、森鴎外と同じく、ほとんど「女性」は使っていません。使っている場合は「にょせう」のルビがあります。「にょしょう」です。
以下は「こころ」(初出は大正三年)から。
始め私は理解のある女性として奥さんに対していた。私がその気で話しているうちに、奥さんの様子が次第に変って来た。
もしそれが詐いつわりでなかったならば、(実際それは詐りとは思えなかったが)、今までの奥さんの訴えは感傷センチメントを玩もてあそぶためにとくに私を相手に拵えた、徒な女性の遊戯と取れない事もなかった。
「こころ」ではこの二カ所です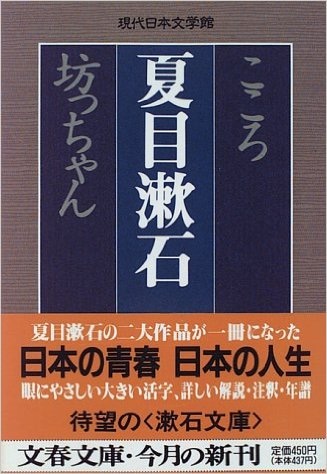 が、最初に出てきた「女性」にルビをつけ、あとは省略したものかと思われます。つまり、二番目も「にょしょう」と読むのでしょう。
が、最初に出てきた「女性」にルビをつけ、あとは省略したものかと思われます。つまり、二番目も「にょしょう」と読むのでしょう。
「それから」(明治四二年初出)ではさらに多数の「女性」を使ってますが、いずれも「にょせう」のルビがついています。
芥川龍之介も「にょしょう」と読む「女性」をよく使用しているのですが、これは時代設定が古い小説が多いためでもありそう。よって、発表された時代の言葉遣いを表していると必ずしも言えないのですが、これより古い時代は「にょしょう」であったことまではわかります。
このことを踏まえると、「女性」の読みは「にょしょう」から「じょせい」へ変化したものと推測できます。
『或る女』に見る「女」
![]() 明治末期から大正初期が初出である有島武郎の『或る女』の場合は、本文で個人を特定したところでは「女」とともに「女性」を多用。
明治末期から大正初期が初出である有島武郎の『或る女』の場合は、本文で個人を特定したところでは「女」とともに「女性」を多用。
タイトルの段階では、どこの誰かわからない「ある〜」ですから、読者にとっては不特定の個人。そのため、「女性」は使いにくかったかもしれない。主人公は十九歳なので「女子」エリアでありながら、それを特定できていない段階では「女子」も使いにくく、今でも同様のタイトルにする時は「ある女」にするしかないかもしれないですけど、本文中でも「女」を使っています。
会話文で「女」が多用されているのは当然として、地の文章で使用されている「女」の意味はおおむね説明ができます。
そして少しひがんだ者たちは自分の愚を認めるよりも葉子を年不相当にませた女と見るほうが勝手だったから。
女の本能が生まれて始めて芽をふき始めた。
葉子の母が、どこか重々しくって男々しい風采をしていたのに引きかえ、叔母は髪の毛の薄い、どこまでも貧相に見える女だった。
「報正新報」といえば田川法学博士の機関新聞だ。その新聞にこんな記事が現われるのは意外でもあり当然でもあった。田川夫人という女はどこまで執念く卑しい女なのだろう。
倉地はもう熱情に燃えていた。しかしそれはいつでも葉子を抱いた時に倉地に起こる野獣のような熱情とは少し違っていた。そこにはやさしく女の心をいたわるような影が見えた。葉子はそれをうれしくも思い、物足らなくも思った。
この本に出てくる「女」のすべてをきれいに説明できるわけではないですが、ここに挙げた例ではそれぞれに説明がつきます。

(残り 1509文字/全文: 2931文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。








外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ