マネや黒田清輝を猥褻とする人々にさえ対抗できないセクハラの定義—京都造形大学に対する訴訟[2]-(松沢呉一)
「大学という聖域はもはや存在しない。残るはロフトプラスワンだけ(笑)—京都造形大学に対する訴訟[1]」の続きです。
京都造形大学に対する訴訟は触れにくい
![]() 京都造形大学の公開講座を受講した人が訴えた件については、Facebookで簡単には触れましたが、前回そうしたように、芸術論をテーマとした講座を受講する際の原告の姿勢を批判することはできても、裁判には踏み込みにくい。原告側の姿勢は明らかにされているのに対して、学校側の事情は何もわからないので。
京都造形大学の公開講座を受講した人が訴えた件については、Facebookで簡単には触れましたが、前回そうしたように、芸術論をテーマとした講座を受講する際の原告の姿勢を批判することはできても、裁判には踏み込みにくい。原告側の姿勢は明らかにされているのに対して、学校側の事情は何もわからないので。
京都造形大学は学則や職員就業規則等は公開していますし、よくあるアバウトなガイドラインは公開されていますが、京都造形大学のセクハラの規程がどうなっていたのか、その規程は一般向けの講座である「藝術学舎」にも適用されるものだったのか、あるいは「藝術学舎」用の規程があるのか、報告書というのがどういうものだったかがわからず、それ次第では学校側が負ける余地がありそうです。
 ハラスメントの規程は見当たりません。わからん以上、判断がつかない。
ハラスメントの規程は見当たりません。わからん以上、判断がつかない。
その上、会田誠は「寝耳に水」と言っていますから、通常の手続きが踏まれていないのか? 「通常の手続き」というのは、学内のなんとか委員会みたいなものが両者の意見を聞き、規程に基づいて判断して、処分を決定する、といった手続きです。
その内容がセクハラだったかどうかを論じるまでもなく、防止策のガイドラインに反していることを学校側が認めたってことなのかとも思いますが、それもわからないので、どうしようもない(防止策の規程と処分の規程は別という話は「防止策の定義は判定基準にならない—セクハラって何?[4]」を参照のこと)。
講義内容がセクハラだったということで講師を訴えた訴訟だったら勝ち目はないでしょうから、訴訟を起こしたのは、学校側がガイドラインに照らしてセクハラに該当するとの報告書を出している点、示談の際に「その上でお互い関わり合いを持つことをやめる」という項目があった点の二点を踏まえてのことでしょうけど(弁護士ドットコムによる)、現段階ではそれらの経緯が事実だったのか、適正な手続きだったのかどうかもわからんのです。
ゆるゆるのハラスメント定義に疑問を抱かないすべての大学の問題
![]() 以上のことからして、裁判については踏み込みようがないのですが、京都造形大学を離れて、原告のような考え方、姿勢の人が出てきてしまった場合、ゆるゆるの定義を採用している学校では、ハラスメントと認定され、教員・講師が処分される可能性があることを今回のことは明らかにしたと言えます。
以上のことからして、裁判については踏み込みようがないのですが、京都造形大学を離れて、原告のような考え方、姿勢の人が出てきてしまった場合、ゆるゆるの定義を採用している学校では、ハラスメントと認定され、教員・講師が処分される可能性があることを今回のことは明らかにしたと言えます。
社会全体が改めてセクハラの基準についての議論をやっておく必要がありそうです。と私がいくら言おうと無駄だとわかりつつ言っておきます。
 「本人が不快だと思ったらセクハラ」なんて、定義としての体を為していない定義に疑問を抱かない人々を私はずっと批判してきました。
「本人が不快だと思ったらセクハラ」なんて、定義としての体を為していない定義に疑問を抱かない人々を私はずっと批判してきました。
今回のような例が出てくることは米国の先例が示していました(ナディーン・ストロッセン著『ポルノグラフィ防衛論』参照)。それを読む前から、私もそのことに気づいて批判をネットで書いていました。
それを回避する定義を作っておくべきであり、それをやっていない大学については自業自得としか言いようがない。
考えることも調べることもせず、「複雑な問題に簡単な答えを求める」大学は次々訴えられて消えていけばいいと思います。
表現を考える気があれば、学問の自由を守る気があれば、いい加減な規程を作って、「生徒のためのいい学校」だと自己満足していられるはずがないのです。
※Wikipediaより

(残り 2007文字/全文: 3558文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。






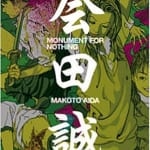

外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ